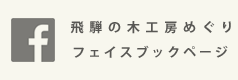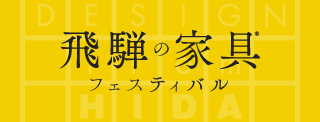つくり手の『道具』
2022年09月15日
cocoon工房は、繭から糸をとり植物で染めて
布を織ることを楽しむ工房です。

廃校となった秋神小学校の図工室には、
織機やさまざまな道具が所狭しと並んでいます 残念ながら養蚕のほうは、只今行っていませんが、養蚕をしていたなごり、ご覧頂けます。
最近は、着尺織機はお休みして、
繭綿を色とりどりに染め
思いのままに色をmixしながら
太い糸を紡ぎ織っています。

思いのままに 繭綿を選び重ねる

ミシンのモーターが動力の糸紡ぎ機

今までにないカラフルな布が織り上がっています。
工房巡りでは、この様な糸紡ぎから小さい布を
織って頂くワークショップを開催します。
ぜひ一度、体験してみたい方は、
お気軽にご参加下さい。

昨年のワークショップ
詳細につきましては、
このブログにてお知らせします。
または、お電話かメールでお問い合わせ下さい。
 090-6802-2878
090-6802-2878
 elephantojjo@docomo.ne.jp
elephantojjo@docomo.ne.jp
~
布を織ることを楽しむ工房です。

廃校となった秋神小学校の図工室には、
織機やさまざまな道具が所狭しと並んでいます 残念ながら養蚕のほうは、只今行っていませんが、養蚕をしていたなごり、ご覧頂けます。
最近は、着尺織機はお休みして、
繭綿を色とりどりに染め
思いのままに色をmixしながら
太い糸を紡ぎ織っています。

思いのままに 繭綿を選び重ねる

ミシンのモーターが動力の糸紡ぎ機

今までにないカラフルな布が織り上がっています。
工房巡りでは、この様な糸紡ぎから小さい布を
織って頂くワークショップを開催します。
ぜひ一度、体験してみたい方は、
お気軽にご参加下さい。

昨年のワークショップ
詳細につきましては、
このブログにてお知らせします。
または、お電話かメールでお問い合わせ下さい。
 090-6802-2878
090-6802-2878 elephantojjo@docomo.ne.jp
elephantojjo@docomo.ne.jp~
つくり手の「道具」椅子張り&皿 とらまめ
2020年06月19日
今年から木工房の会の正式メンバーにいれてもらいました とらまめ 北奥です。


こうゆうの作ったり、正円じゃない皿を旋盤で挽いたり、普通に張り屋したりしています。
ウェブ http://toramame.com です。
今回のリレーブログ当番はあんま被らなそうな椅子張りの道具を紹介してみます。

タッカーはドイツ製のBeA やばい
やばい
引っ込んだ溝にも打てるように嘴と、針の送りがスムーズになるように内部をちょっと改造してあります。
タッカーの針を抜くのにはいろいろ試した結果、車の内装剥がすやつが1番好きです。

目打ち類は、転がったり落ちたりしないように服着せたり三角に削り落としたりしてます。
細長いハンマーはマグネットハンマーという釘がくっつくハンマーです。
昔の職人は釘を口に含んでおいて1本ずつ出してこれにくっつけて張ってたらしくて、やってみたけど、めっちゃムズ!てゆうか飲み込む〜〜てなって私は布に刺して自立させたところをこのハンマーで打っています。
あと150mmの定規!縫製関連の人のはだいたいなんか結んであるか可愛いストラップついてて人の見るの楽しいです。
こんなもんでしょうか…
最後に展示の告知です
八犬堂ギャラリーさん主催のKENZANに出展します。
6/25〜29、販売は7/5まで
http://kenzan.jp/


本当は実物展示だったのですがコロナウイルスの影響でオンライン開催です。よければ
それでは皆さまよい週末を


こうゆうの作ったり、正円じゃない皿を旋盤で挽いたり、普通に張り屋したりしています。
ウェブ http://toramame.com です。
今回のリレーブログ当番はあんま被らなそうな椅子張りの道具を紹介してみます。

タッカーはドイツ製のBeA
 やばい
やばい引っ込んだ溝にも打てるように嘴と、針の送りがスムーズになるように内部をちょっと改造してあります。
タッカーの針を抜くのにはいろいろ試した結果、車の内装剥がすやつが1番好きです。

目打ち類は、転がったり落ちたりしないように服着せたり三角に削り落としたりしてます。
細長いハンマーはマグネットハンマーという釘がくっつくハンマーです。
昔の職人は釘を口に含んでおいて1本ずつ出してこれにくっつけて張ってたらしくて、やってみたけど、めっちゃムズ!てゆうか飲み込む〜〜てなって私は布に刺して自立させたところをこのハンマーで打っています。
あと150mmの定規!縫製関連の人のはだいたいなんか結んであるか可愛いストラップついてて人の見るの楽しいです。
こんなもんでしょうか…
最後に展示の告知です

八犬堂ギャラリーさん主催のKENZANに出展します。
6/25〜29、販売は7/5まで
http://kenzan.jp/


本当は実物展示だったのですがコロナウイルスの影響でオンライン開催です。よければ

それでは皆さまよい週末を

作りて手の『道具』 杼
2019年09月16日
繭から糸へ糸から布へ
COCOON工房です。
ご紹介する道具は、

『杼』
ヒ と呼ばれるこの道具は
機を織る時に緯糸を 織り込むのに使用します。

いろいろな形があって
1番愛着のある大切な道具の1つ
あなたなしでは、織れないわ~(笑)
手放せませんよ〜。
2019年06月25日
白百合工房の上野です。
正確に加工するために、正確に測ること、正確に墨付けをすることは絶対条件です。

部材を測るための七つ道具です。

ボランチのノギスとトップ下の罫書きゲージです。
床に落としたら、多分泣きます。

トンボみたいですが、頼もしい相棒です。

部材への墨付けが楽チンです。
あなたなしでは、生きていけないわ笑
正確に加工するために、正確に測ること、正確に墨付けをすることは絶対条件です。

部材を測るための七つ道具です。

ボランチのノギスとトップ下の罫書きゲージです。
床に落としたら、多分泣きます。

トンボみたいですが、頼もしい相棒です。

部材への墨付けが楽チンです。
あなたなしでは、生きていけないわ笑
Posted by 飛騨の木工房の会 at
08:46
│■つくり手の「道具」
焼き物の道具
2019年06月15日
山口町で焼き物をしております しずく窯の中西です。
近頃工房に遊びに見える方にろくろを回し手づくりで同じ大きさ、形のものがよくできますね~と質問されることが多いです
本当の名人は手の感覚だけでピタリとおなじものができるのかもしれませんが 残念ながらそんな技術はありませんので
色々道具を使っています。


作る作品に合わせて様々な形のコテやヘラと呼ばれるもの 器の口径、深さをはかるトンボです
コテは器の内側の形の中心からほぼ半分の形に制作します。ろくろをひく場合このように使います。 ちょっとわかりにくいかも?
ある程度形ができあがったところで口径と深さを確認します。

これで簡単に同じものをろくろで制作することができます!
道具は全て自分で手作りします 木や竹を削っての道具作りも楽しいものです。
近頃工房に遊びに見える方にろくろを回し手づくりで同じ大きさ、形のものがよくできますね~と質問されることが多いです
本当の名人は手の感覚だけでピタリとおなじものができるのかもしれませんが 残念ながらそんな技術はありませんので
色々道具を使っています。
作る作品に合わせて様々な形のコテやヘラと呼ばれるもの 器の口径、深さをはかるトンボです
コテは器の内側の形の中心からほぼ半分の形に制作します。ろくろをひく場合このように使います。 ちょっとわかりにくいかも?
ある程度形ができあがったところで口径と深さを確認します。
これで簡単に同じものをろくろで制作することができます!
道具は全て自分で手作りします 木や竹を削っての道具作りも楽しいものです。
つくり手の「道具」
2019年05月17日
一之宮町在住のガラス作家・神代&小曽川です。
『火』と『水』を使う道具をご紹介します。
『火』

こちらは酸素バーナーを使用しているところです。

溶けたガラスを直接触ると火傷をしてしまうので、ピンセットやカーボン製のコテなどでガラスを触って形づくっていきます。また、火との距離が近いため、燃えにくい素材の手袋をして作業しています。
『水』


こちらはガラスを切削・研磨するための道具。
水を流しながらガラスを加工するため、コールドワーク(Coldwork)と呼ばれています。
これからの暑い季節には快適な作業です!
『火』と『水』を使う道具をご紹介します。
『火』

こちらは酸素バーナーを使用しているところです。

溶けたガラスを直接触ると火傷をしてしまうので、ピンセットやカーボン製のコテなどでガラスを触って形づくっていきます。また、火との距離が近いため、燃えにくい素材の手袋をして作業しています。
『水』

こちらはガラスを切削・研磨するための道具。
水を流しながらガラスを加工するため、コールドワーク(Coldwork)と呼ばれています。
これからの暑い季節には快適な作業です!
集まってくる道具達
2019年04月30日
木版画を細々と続けて二十年程。
初めは小学生が使うような 一本400円程度の彫刻刀を使っていた。
自宅に、亡くなった父が毎年、年賀状を彫っていた彫刻刀が出てきて
それが初めての本格的な、彫刻刀との出会いだった気がする。

研ぐのが大変だからと、使い捨ての方がいいと
300円程度の安い彫刻刀を買ったり、
でも、 「版画やっとるんやろ」とか言われ

「これ使わんか・」と
ありがたいことに、ただで
誰かのものを譲り受け
職人さんが使うような、彫刻刀が集まってきた。
でも、ちゃんと研がないとダメなんだ。
知り合いは、約五万ほどの電気の研ぎ機を
もうやらないからと、もらったという人もいる。
そういう人は、やっぱり 使いこなすだけの技量があり
その人をお応援してくれてる、プレゼントなのかな・・・と
思ったりする。
あなたには、集まってくる道具達 物達ありますか
初めは小学生が使うような 一本400円程度の彫刻刀を使っていた。
自宅に、亡くなった父が毎年、年賀状を彫っていた彫刻刀が出てきて
それが初めての本格的な、彫刻刀との出会いだった気がする。
研ぐのが大変だからと、使い捨ての方がいいと
300円程度の安い彫刻刀を買ったり、
でも、 「版画やっとるんやろ」とか言われ
「これ使わんか・」と
ありがたいことに、ただで
誰かのものを譲り受け
職人さんが使うような、彫刻刀が集まってきた。
でも、ちゃんと研がないとダメなんだ。
知り合いは、約五万ほどの電気の研ぎ機を
もうやらないからと、もらったという人もいる。
そういう人は、やっぱり 使いこなすだけの技量があり
その人をお応援してくれてる、プレゼントなのかな・・・と
思ったりする。
あなたには、集まってくる道具達 物達ありますか
桐の乾燥
2019年04月29日

kino workshop 片岡です。
先日近所のおじいさんから稲架木(はさぎ)と稲架木をしまってあった小さな小屋を譲ってもらったときに、
うちの裏にあって3年程前に伐採した桐の丸太をいただきました。。
桐は灰汁を抜かないと黒くなってしまうそうで、風通しのよい場所で屋根をせず雨に当てて乾燥させるそうです。
早速製材して、いただいた稲架木を使って板をたてかけてみました。
桐の乾燥は初めてなのでどう仕上がるか楽しみです。